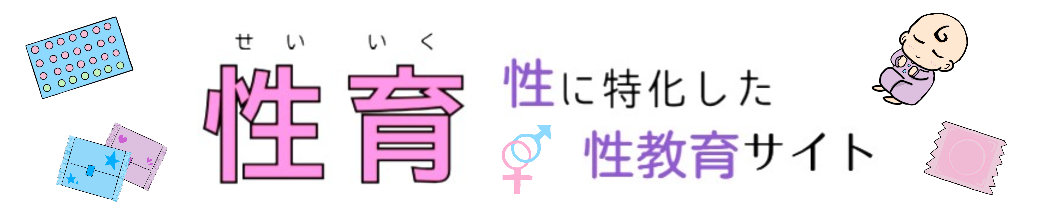最近、友達やSNSでの会話、テレビ番組などで性の話題があふれていると感じていませんか?
「みんな、性についてすごくオープンで楽しそう。でも、私はどうしても話についていけない」
そんなふうに感じているあなたへ。
この記事では、産婦人科医であり心理カウンセラーでもある私が、性に対してオープンすぎる周囲にどう向き合えばよいのか、また、自分自身の気持ちとどう折り合いをつけていけばよいのかを、やさしく解説していきます。
他人と違うことで不安になる必要はありません。あなたの感じ方には、ちゃんと理由があり、それは決して間違いではないのです。
性の話題についていけないのはおかしい?
自分の「心の声」を尊重してみよう
性の話題に対して興味がわかない、居心地の悪さを感じる。
それはあなたの感受性や過去の経験、価値観によるものであり、「おかしい」ことではありません。
誰にでも「心地よい話題」と「そうでない話題」があるのは当然のことです。性に関する話題が苦手なのは、ごく自然なこと。
無理に周りに合わせようとして心をすり減らす必要はありません。
オープン=正しい、ではない
近年は性に対してオープンであることが「進んでいる」「自立している」と受け取られがちです。
しかし、オープンであることが常に正しいとは限りません。
自分の価値観やペースを守ることも、立派な「自分らしさ」です。
周囲とどう付き合っていけばいい?
距離の取り方を工夫する
どうしても性の話題が苦手だと感じるときは、その場から少し距離をとるのも方法のひとつです。
無理に話題に乗らず、聞き役にまわる。
もしくは、話題が変わるのを待つ、トイレに立つなど、自然な形で場を離れるのもOKです。
自分の気持ちを伝えてもいい
信頼できる相手であれば、「そういう話はちょっと苦手で…」と正直に伝えることも大切です。
それだけで心が少し軽くなることもあります。
あなたの気持ちを否定する人より、受け止めてくれる人を大切にしてください。
共感を求めすぎなくていい
「みんなと同じように楽しめない自分はおかしいのかな?」と感じるかもしれません。
でも、人それぞれの感性があり、得意・不得意があります。
「共感できない自分」に罪悪感を持つ必要はありません。
性に対する感受性は人によって違う
性的関心の強さには個人差がある
性に関して「興味が強い人」「ほどほどの人」「興味がほとんどない人」などさまざまです。
このどれもが正常の範囲内であり、優劣はありません。
あなたがその話題に関心を持てないことが、あなたの「個性」なのです。
自己理解が安心感をもたらす
性の話についていけない自分を理解し、認めてあげることで、不安はぐっと軽くなります。
「これが私の自然な姿なんだ」と納得できるだけで、周囲との違いにおびえることが減っていきます。
無性愛という考え方もある
無性愛(アセクシュアル)とは?
無性愛とは、他人に対して性的な魅力を感じにくい、あるいはまったく感じない性のあり方です。
近年、LGBTQ+の中に「A(アセクシュアル)」として認識されるようになり、多様な性の一部として理解が進んでいます。
性に対する違和感や関心のなさを言語化できることで、心が楽になる人も少なくありません。
ラベリングは自由でいい
必ずしも自分にラベルをつける必要はありません。
「自分は無性愛かも」と思うことで気持ちが楽になるなら、それを選ぶのも良いでしょう。
一方で、「どのラベルにも当てはまらない」と感じるなら、それもまったく問題ありません。
性について悩んだらどうしたらいい?
専門家に話すことも選択肢の一つ
心療内科やカウンセラー、婦人科などで相談することは、性に関する悩みを整理するうえでとても有効です。
あなたの気持ちを否定せずに受け止めてくれる人がいることで、気持ちが整理されていきます。
似た悩みを持つ人の声を探す
無性愛や性の話題に違和感を持つ人の体験談を読んだり、SNSなどで発信を見たりすることで、「自分だけじゃない」と感じることができます。
自分と似た感覚を持つ人がいると知るだけでも、心がぐっと軽くなります。
自分を大切にするということ
「普通」に合わせる必要はない
「みんながこうだから、私もこうすべき」という思い込みに縛られる必要はありません。
あなたは、あなたのままで良い。
性の話題に限らず、どんなことでも「無理をしない」ことが、心の健康にはとても大切なのです。
自分の価値観を信じていい
自分の気持ちに正直に向き合い、それを尊重することは、あなたの人生をより豊かにします。
周りがどうであれ、「自分はこう感じている」という心の声を大切にしてください。
最後に伝えたいこと
周りが性にオープンすぎてついていけないと感じるのは、あなたの繊細さや誠実さのあらわれです。
その気持ちは決して否定されるものではありません。
あなたは何も間違っていないし、置いてけぼりでもない。
周囲のペースに惑わされず、自分自身を大切にしながら、自分の感性と向き合っていきましょう。
少しずつでも、「自分のままでいい」と思える時間が増えていくことを願っています。