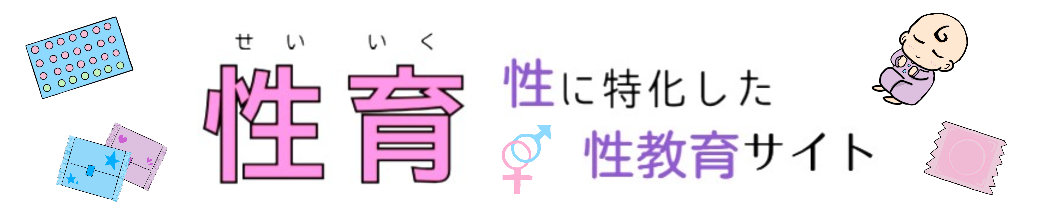「こんな性癖、人には言えない」 「やめたいのに、やめられなくて苦しい」…そんな思いを抱えながら一人で悩んでいませんか?
性癖に関する悩みはとてもデリケートで、誰かに相談しづらいもの。
しかし、恥ずかしいと思う必要はありません。
この記事では、産婦人科医であり心理カウンセラーでもある立場から、「自分の性癖をどう理解し、罪悪感とどう付き合っていくか」について、優しく具体的にお伝えします。
あなたが少しでも心を軽くし、自分を責めずに前向きになれるようにサポートします。
「変な性癖」とは何か?
性癖は誰にでもある
性癖とは「性的嗜好」のこと。
誰でも多少なりとも、性的な好みや傾向を持っているものです。
- 特定のシチュエーションが好き
- 特定の衣装や部位に興奮する
- 支配や服従の要素がある
- 匂いや声、雰囲気などに惹かれる
こうしたものは非常に幅広く、「普通」「異常」という明確な線引きはありません。
人間の性の多様性はとても豊かで、その背景には文化、育った環境、過去の体験、脳の特性などさまざまな要因が絡み合っています。
なぜ「恥ずかしい」と感じるのか
- 社会的な価値観(「これが正しい性」と刷り込まれたもの)
- 過去に否定された経験
- 自分でも理解できない「なぜこう感じるんだろう?」という戸惑い
こうした要因が重なることで、「自分はおかしいのでは」と思い込んでしまうことが多いのです。
また、インターネットやメディアに溢れる「理想の性」のイメージと自分の嗜好を比較し、「ズレている」と感じてしまうケースも珍しくありません。
性癖がやめられない理由
性癖は「心の栄養」のひとつ
性癖は単なる「性の趣味」だけでなく、心の奥底の「安心感」や「自分を癒すもの」として働いている場合があります。
- ストレス発散
- 寂しさや不安を埋める
- 自己肯定感を得る手段
- 自分らしさを確認する方法
このように、性癖は無意識に心を守る役割を担っていることがあるため、「やめよう」と思っても簡単には消えないのです。
やめようとするほど強くなる
心理学で「シロクマ実験(思考抑制の逆効果)」と呼ばれる現象があります。
考えないようにしようとするとかえって頭から離れなくなるもの。性癖も同じで「やめなきゃ」と焦るほど余計に意識が強まってしまうのです。
この悪循環は「抑圧→反動→罪悪感→さらに抑圧」というサイクルを生み、心に負担をかけてしまいます。
性癖との向き合い方
「悪いもの」と決めつけない
まずは「性癖=悪」「自分は異常」という思い込みを緩めましょう。
医学的・心理学的には、「本人や他人を傷つけず」「日常生活に支障が出ない」範囲であれば、性癖自体は問題ありません。
自分を責めるのではなく、「自分はこういう傾向があるんだな」と受け止める姿勢が第一歩です。
どうしてその性癖があるのか振り返る
- 初めてそれに興奮したのはいつ?
- その時の気持ちや状況は?
- 性癖を通じて得られる感情は?
- 過去の出来事や環境とどう関係している?
自分史を丁寧に振り返ることで、「性癖の背景」が見えてきます。
これにより、「単なる欲望」ではなく「心の癒しや安心感」と理解できるようになり、罪悪感が薄まります。
安心できる誰かに話す
信頼できる友人やパートナー、もしくは専門のカウンセラーに打ち明けることで、「受け止めてもらえた体験」が自己肯定感につながります。
話すことで「自分だけじゃない」「わかってくれる人がいる」と実感でき、孤独感が和らぎます。
カウンセラーや医師は守秘義務があるため、安心して本音を話せます。
性癖とのバランスを取るコツ
やめるより「上手につき合う」
性癖は完全になくす必要はありません。
- 日常生活に支障がない頻度で楽しむ
- 罪悪感なく「安全に」満たす方法を探す
- 危険や違法行為を避けるルールを決める
こうした「適度な距離感」で向き合うことで、心も穏やかになります。
別の心の栄養を増やす
性癖が「心の栄養」となっているなら、他にも自分を満たせる方法を増やしてみましょう。
- 趣味や運動、創作活動
- 誰かとの温かなつながり
- 自分を認める習慣(褒め日記やマインドフルネス)
性癖への依存度が下がり、「性癖だけに頼らない自分」に近づいていきます。
専門家に相談する目安
次のような場合は、専門家のサポートを受けることでより楽になります。
- 性癖が日常生活や人間関係に支障をきたしている
- 自分や他人を傷つけそうで不安
- 罪悪感や自己否定感が強く、気分が落ち込みやすい
産婦人科、精神科、心理カウンセラーなどが適切に対応します。診察や相談はプライバシー厳守なので安心して大丈夫です。
治療では「性癖を消す」のではなく、「苦しさを減らし、自分らしく生きる方法」を一緒に探します。
おわりに
性癖は「異常」でも「悪」でもありません。
むしろ「自分を理解し、大切にするヒント」と考えることができます。
焦らず、無理せず、少しずつ自分との関係を整えていきましょう。
あなたは「そのままでも大丈夫な存在」です。